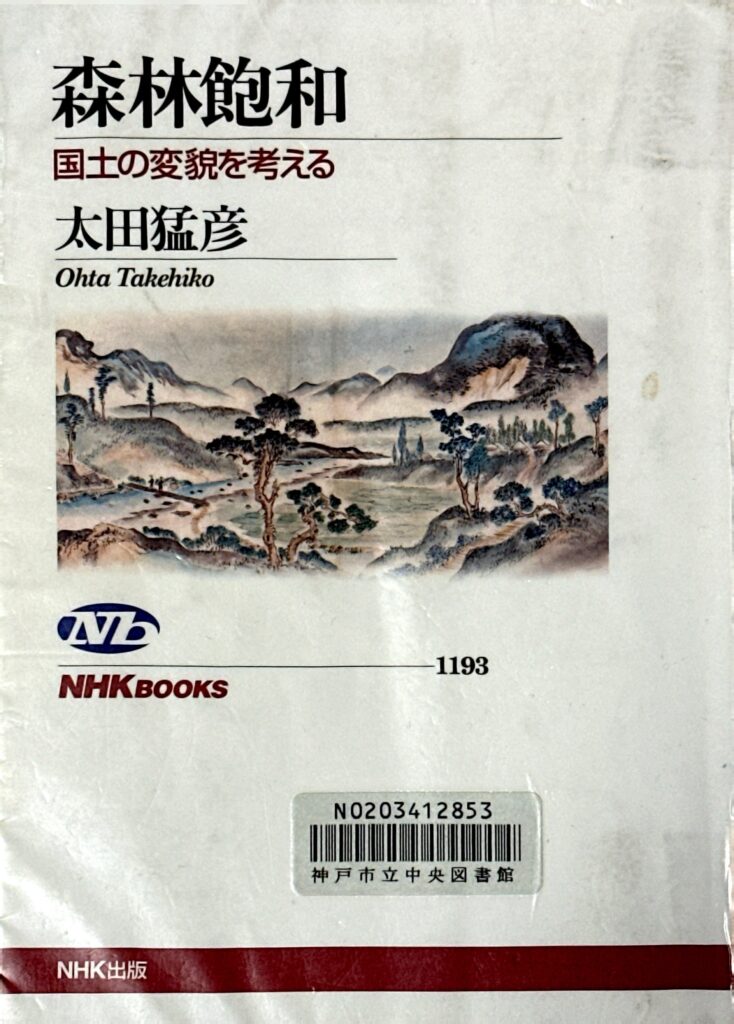
この本を読もうと思ったきっかけをはっきりとは思い出せないのであるが、おそらく植林された莫大な量の森林の手入れがなされず荒れている現状を詳しく知りたいと思ったからではないかと思う。これまで知らなかったことや知っていると思っていたことが間違っているのが分かり、大変興味深い本であった。杉から出る花粉の量が天気とともに予測され、それに対する注意喚起が出るほど花粉症の人が激増して久しい。かく言う私自身も、最近は程度は軽くはなったが、春になるとアレルギーに悩まされる一人である。この本にはしかし、手入れされていない杉を手入れすれば花粉症が収まる、という単純なことは一切書かれていない。
著者はまず、日本の海岸線に見事に生え、日本の三大松原、と言われるほど名勝と呼ばれる松原が人工林であることを説明し、アカマツではなくクロマツである理由とそれらが植えられるにいたった背景、そして植えられてからのその地域の成り行き、変貌について述べている。クロマツは貧栄養土壌を好み、農民に落葉や生枝を提供した。それらは砂防林となり、潮風を防ぐ役目を担った。そこから日本の山が江戸時代から戦後にかけて、どれほどのはげ山であったかを歴史的に説明する。はげ山になると土砂崩れが起こる。そして海へ向かって流れ出た土砂が川底を盛り上げ、天井川となることや、一言で土砂崩れといってもいろいろな種類があること、植林を盛んに行い土砂崩れは少なくはなったが、今度は逆に山から河、そして海に砂が流れなくなった(砂防ダムの影響もあり)がために、砂浜が減退し海岸線が変わっていると述べる。これら一連の事実がこの本のタイトル、「森林飽和」につながっている。
著者は、このとてつもなく大きな問題をどのように解決すればよいか試案を出しているが、「持続可能な」方法、という言葉を目にして、私は一挙に期待が薄れてしまった。地球温暖化という主張を疑わず、それを解決するために云々、と言われると、その人の知性を疑わなければならないようになってしまった自分がいる。閑話休題。
著者は、渓流生態系の保全のためには土砂の移動を許さなければならない、(p-243)というが、これは土砂崩れを防ぐのとは逆の動きになる。そこで、「新しいステージ」として、土砂災害のないように山崩れを起こさせ、流砂系に土砂を供給することとなるのだろうか(P-243)、と結論を出すことを避けている。確かにそのとおりである。二つの相反することを同時に成立させる必要がある難題である。
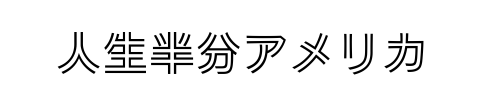

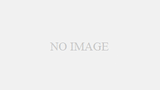
コメント