
「ノモンハン」と聞くと、半藤一利や五味川純平の小説で取り上げられている史実で、日本軍がぼろ負けをした不要な戦いだった、くらいしか知らなかったが、実際はその逆で、日本軍(関東軍)はソ連に勝っていたという話を知り、詳しく知りたいと思ってこの本を借りた。1991年にソ連が崩壊するまで隠されていた、ノモンハンの戦いについての記録が徐々に公開されるについて、小説で国民に広まったこれまでの認識が必ずしも正しくないことがわかってきたのである。実際に戦った人々にとっては、ようやく陽の光を見るような思いだろう。記録が明らかにされ、この戦争に関わった人たちが史実を克明に追求することによって、作家たちが書かなかった、または隠したかった事実が出てきていると思われる。
ノモンハンは、モンゴル人民共和国と満州国の北部国境にあり、ソビエトに近く、緯度で言うと日本の樺太の南の端あたりに位置する。「ノモンハン事件」と呼ばれるのは、これが戦争ではなく、満州国に侵入してきたソビエト軍と関東軍の数ヶ月にわたる、昭和14年に起きた攻防である。この本の副題のとおり、関東軍がソ連軍を撃破した記録が詳細に並べられている。ノモンハン戦はなぜ起きたか、なぜこの荒野で戦う必要があったかは、ソ連が国境侵犯をしたからに他ならないが、多くの著者はこれに挑戦した。日本の対応を非難する一方、ソ連の満州国への爆撃やソ連の唱える国境線から20キロ以上入ったソ連側の国境侵犯を正しいとは述べていない。
原史修正会に属する著者の2人は第2章で、事件に関連するありとあらゆる記録をもとに、何が起こったかを解き流すために戦闘経過を時系列に明らかにしている。戦闘に参加したした師団の種類、出動人員、使用した兵器、航空機、戦車の数量など、第一次ノモンハン事件が始まった昭和14年5月11日の関東軍による動きがあった時点から毎日、各小隊、中隊、歩兵隊などなど、地域に散らばる様々なぶたいで記録された日記を元に、それぞれの場所で、何時に何があったかと言う細かい記録、報告が詳細に追って書かれている。6月18日(日)には、第二次ノモンハン事件が発生し、その日の日本の飛行機がソ連の飛行機より数倍も勝っていたとか、ソ連の戦車が日本の機関銃で穴が開いただとか、様々なことが書かれている。
これらに目を通す限り、とても日本軍が負けたとは思えない。ソ連兵の記述について紹介する。「悲惨なソ連兵士、むしろ悲惨なのは赤軍兵士だった。畑にいたのは拉致されて兵士にされ、彼らは全く戦意がなく、戦争目的もなく格闘術も知らずに銃と手榴弾を持たされ、演習と称して戦場に連れてこられ、内務将軍の監視下、全身に刺さられた接近して、手榴弾を投げるだけの歩兵で銃剣術は知らないので、日本軍の突撃には逃げるしかなく、泣き顔をあげながら逃げた。あまり逃げすぎると、内務将軍に射殺され、火炎放射機で焼かれた。」(p-164)[
9月15日、ソ連が関東軍の停戦案を受託、ノモンハン事件が集結した。9月16日に停戦の発表がされた。この時このような記述がある。219ページ「9月15日ソ連受諾日本は恐ソ病にかかっていたが、ソ連はそれ以上に恐日病にかかっていた。これはすべての班での日本軍の戦闘によるものである。この日ソ連機44機撃墜、日本損害5機。」(p-219)別の本で読んだ辻正信少佐についての記述も少しあった。作家たちは、下克上的に参謀が司令官を振り回したと書き、辻正信参謀が事件を引き起こし、作戦を誤ったように書いているが、事件を起こしたのはスターリンであり、見通しを誤ったのは第6軍司令官と師団長で、彼らの責任を追及する必要がある。(p-226)
平成元年代ようやく遺族団参戦者により戦績。戦いの後が訪問され、建築業が始められたが、両国とも現地対応の戦史の研究が不十分で、戦跡は未確認地点が多い。この書籍の最後の部分で、「特別解説」としてこの書籍の出版準備中に出版された2冊の本について、「本文中では十分に検討できなかったので、ここに追記すると言うことで、鎌倉英也著の『ノモンハン、隠された戦争』の、事実ではない内容についてひとつひとつ反駁している。誤りを正しておかなくてはいけないと言う態度は素晴らしいと思う。黙っていれば、これが本当になってしまうからだ。目に止まった反駁は以下。「三光作戦は蒋介石が中共を支える地域住民の根絶を目指して行った作戦で、日本には三光などの意味不明な言葉はない。南京虐殺なども住民25万のところに30万人の虐殺などできるわけがない。これも南京占領に伴い、中国兵の防御から解放された人々が集まり、人口が増えているのを見れば明らかである 。」(p-235)「失敗とは何よりもソ連の軍拡侵略主義を無視し、日本が深大策だったのが付箋の悪循環となったのである。」(p-241)5川純平安堂和俊の小説を読んでみようかなと思ったが、その必要はないと感じた。(2025年2月)
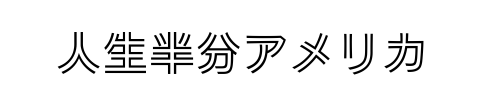

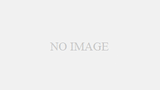
コメント