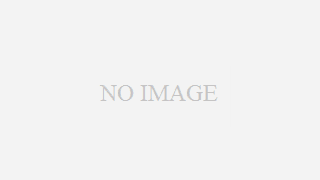 読んだ書籍
読んだ書籍 『誇りある日本文明』高田純
著者は、羅針盤が斉明天皇の時代に考案されたデバイスを基に中国で発明され、大航海時代に普及したという。さっそくAIで調べると、この装置は指南車と呼ばれるもので、羅針盤とは直接関係がなく(磁石を使わない)一定の方角を指し示すものと出た。著者の意...
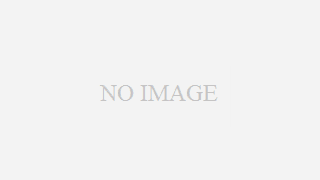 読んだ書籍
読んだ書籍 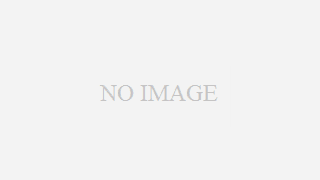 読んだ書籍
読んだ書籍 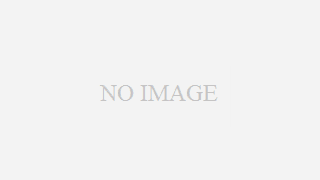 医療・医学
医療・医学 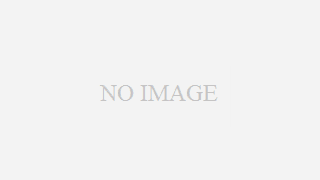 日本史・世界史
日本史・世界史 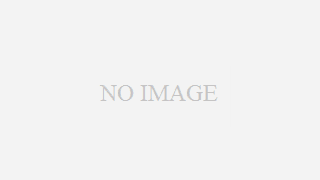 日本史・世界史
日本史・世界史 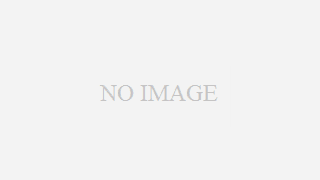 実用書
実用書 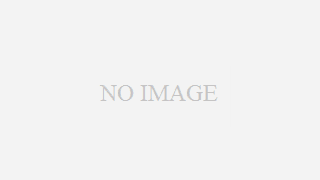 宗教・思想・哲学
宗教・思想・哲学 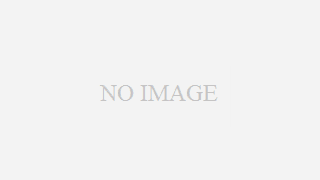 医療・医学
医療・医学 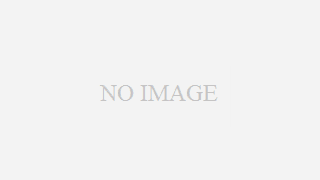 政治・経済
政治・経済 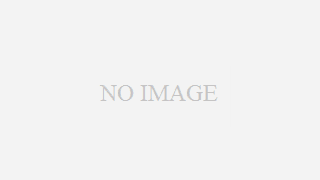 医療・医学
医療・医学